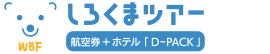鮭(サケ)と鱒(マス)の違い~北海道で長く親しまれる魚、その種類や味わいの違い~
-
- 北海道全域
-
- 最終更新日:2025年10月2日
鮭(サケ)は海、鱒(マス)は川・湖。ただし例外多数

まず「鮭(サケ)」と一口に言っても何を指すのか?日本で流通している鮭の多くは「シロザケ」を指し、秋(9~11月)に産卵のため日本沿岸に回遊し漁の最盛期を迎えるため、秋鮭(アキサケ)、アキアジ(秋味)とも呼ばれます。
一方「鱒(マス)」とは何か?実はマスも「サケ目サケ科」に分類されるサケの仲間。”おおまかに”は、サケは降海型(ある時期に海に出る)、マスは陸封型(淡水で一生過ごす)で分けられたりします。
遺伝子レベルでは明らかに異なる種であるサケとマスですが、その名前で種を完全に区別する事はできません。同じ種でも生態パターンが異なっていたり、サケとマスの種の違いが明らかになる前に名付けられたりしているためです。

1つ面白い例を挙げます。どちらもサケ目サケ科に分類されるサクラマスとヤマメ。両者は元々川で生まれるヤマメの稚魚ですが、成長の過程で違いが出始めます。
個体の大きさ・成長率・ホルモン・水温・遺伝的要素など複合的な要因により、一定以上に成長した個体は銀化(体色が銀色になり、海に適応できるよう体内でも変化が起こる)し、海へ降ります。海に出た個体は、豊富な餌を得てさらに成長し、降海型の「サクラマス」となります。一方、川に残って一生を終える個体は小型のまま「ヤマメ」として成熟するのです。

ちなみにお寿司のネタとして抜群の人気を誇るサーモン。海外からの輸入されたサケや養殖もののサケをサーモンと呼ぶと同時に、本来淡水魚であるニジマスを海水で養殖したものが「トラウトサーモン」と呼ばれており、名前に「サーモン」が付いたとしてもサケ・マスどちらか一概に区別はできません。
この複雑さは、サケやマスが広く親しまれているからこその由縁なのかもしれません。
サケ・マスの種類
秋鮭(鮭・白鮭)
こちらは日本人に身近な鮭である「白鮭」のうち、秋に海からふるさとの川へ戻ってくる個体を指します。北海道や東北地方が主な産地。。産卵に備え、白子や卵の成長のためにエネルギーを使い、そちらに体脂肪を使っているため脂ののりはあっさり。そのためどんな料理にも合い、生臭さも少なめなのが特徴です。
トキシラズ
本来秋にやってくるはずの鮭(秋鮭)が、春から夏という季節外れの時期に日本沿岸にやってきた個体のことを指し、漢字では「時不知」または「時鮭」と書きます。秋鮭は北海道など国内の川で生まれるのに対し、トキシラズはロシア北部のアムール川で生まれ、回遊中にたまたま北海道の沿岸で獲られたもの。まだ若い状態のため、産卵の準備が整っておらず、脂や栄養が全身に乗っているため、味も絶品で高級魚です。
鮭児
未成熟の若いシロザケで、産卵のためにエネルギーが消費されていないため、脂が多く乗った個体を指し、生で食べるとマグロの大トロのような味わいと食感です。主に北海道•知床や羅臼周辺で獲られますが、シロザケ1万尾中1尾以下の割合でしか水揚されないため、市場になかなか出回らない「幻の魚」として重宝されています。
サクラマス
産卵期が近づいてくると体が綺麗な桜色になることからその名がついたという説があります。サケとの違いは漁獲時期。サケは秋に多く漁獲されるのに対し、サクラマスは春のため「春を告げる魚」とも呼ばれています。
カラフトマス
産卵期には背中が大きく盛り上がったように見えることから「セッパリマス」とも呼ばれます。英名は「ピンクサーモン」と呼ばれ、サクラマスと少し混同してしまうところかもしれません。日本国内でカラフトマスの遡上が見られるのはほとんどが北海道の川。ただサケやサクラマスなどと違う点は、遡上してくる川がふるさとの川に限定されていないことのようです。
チップ
北海道では「チップ(アイヌ語で魚の意)」の愛称で知られるヒメマス。ヒメマスは海へ行くことなく淡水域に留まり、一生を湖で過ごします。天然原産が確認されている阿寒湖・チミケップ湖のほか、洞爺湖をはじめ支笏湖や然別湖また道外の湖にも移植放流され広まっています。チップは脂が乗り、川魚にある臭みがなく美味です。
サケとマスの味わいの違い

見た目も似ており、区分もしっかりしてはいないサケとマスですが、では実際に味の違いはどうなっているのでしょうか?

▲参考画像:マスの切り身▲
まずは切り身について比べてみましょう。日本人がよく食べるサケについては、言わずもがなでしょうか。サケは脂がしっかり乗っており濃厚な旨味が特徴なのに対し、マスはどちらかというと淡白であっさりとした味わい。

それではイクラはどうでしょうか?ちなみに「イクラ」=サケの卵と思っている方、サケだけでなくマスの卵もイクラです!スーパーで出回っているもので値段が安いものは、もしかするとマスイクラの可能性も。ちなみにマスイクラは、一般的にサケイクラに比べて粒が小さめで皮が薄く、ねっとりとした食感が特徴。味わいはあっさりとしています。
サケとマスの味わいの違い
身
味の濃さ:サケ>マス
脂の量:サケ多め、マス控えめ
食感:サケしっかり、マス柔らか
おすすめの調理法:サケは焼き魚、刺身、寿司ネタ、スモーク、マスは刺身、ソテー、ムニエル、塩焼き
イクラ
大きさ:サケ(直径約8〜12mm)>マス(直径約5〜8mm)
色:サケは濃橙色、マスはやや薄めオレンジ
味:サケは濃厚、マスはあっさり
北海道で食べたい!サケ・マスをつかった郷土料理
ルイベ

サケやマスなどの魚を一度冷凍させ、解凍せずに刺身にして食べる北海道の郷土料理です。元々はアイヌ民族発祥の料理で、彼らの貴重なタンパク源であるサケを、寒さが厳しい冬の栄養源として雪の中に埋めて保存し、凍ったまま薄くスライスして食べていたことが始まりとされています。語源もアイヌ語の「溶ける」を意味する「ル」、「食料」を意味する「イペ」を合わせた「ルイペ」から。食感は凍っているためシャリっと、そして口の中で段々ととろけていく味わいがたまらない一品です。
三平汁

冬になると食べたくなる「三平汁」。こちらは塩漬けにしたサケやニシンなどを、人参や大根などと一緒に煮込んだ料理です。え?石狩鍋と似ている?と思った方!石狩鍋との違いは、石狩鍋は味噌味で生サケを使う点。三平汁は元々しっかり塩味のついた魚を使用するため、その塩分だけで味つけす をつけるんです。スープはあっさりしておりますが、塩味のしっかりついた魚と味の染み込んだ野菜との組み合わせは絶品。家庭料理としてはもちろんこと、北海道のイベントでもよく振る舞われる定番料理です。
ちゃんちゃん焼き

石狩地方の漁師町で生まれたと言われるこちら。秋から冬にかけて旬を迎えるサケと、たくさんの野菜を蒸し焼きにし、味噌やバター等で味をつけた料理です。筆者自身も大好きで、食卓にも頻繁に乗る料理であり、居酒屋などでお酒のアテとしてもよく合う料理です。北海道では1年を通して食べられており、簡単に作れる上に見た目も豪華、そして野菜もしっかり取れるため、栄養面でも申し分ない料理です。良いサケが手に入ったら、ぜひ作ってみてください。
チップの塩焼き

産まれた湖で一生を過ごす事から湖ごと特産物としてブランディングもされているチップ。チップの塩焼きは、川魚特有の臭みがなく、脂がのり濃厚な身をシンプルに味わえる料理。特に支笏湖で獲れるチップは「支笏湖チップ」と呼ばれ、地元の人や観光客にも愛されており、塩焼きのほか、寿司ネタとしても愛食されています。
こちらの関連記事もどうぞ
姉妹サイトのご紹介(よかったら見てね)